日本庭園と文芸世界
日本庭園と文芸世界
日本庭園の特色
一般の日本人に、日本の代表的な庭園を一つ挙げなさいという質問をした場合、恐らく、次の三つの内のどれかの名が挙がるのではないかと思う。一つは、京都・龍安寺(りょうあんじ)の石庭。もう一つは、日本三名園(金沢の兼六(けんろく)園(えん)、岡山の後(こう)楽園(らくえん)、水戸の偕(かい)楽園(らくえん))のどれか。そして三つ目は、京都及び京都周辺の修学院(しゅうがくいん)離宮(りきゅう)、仁和寺(にんなじ)、円通寺(えんつうじ)などの借景庭園である。
一つ目の龍安寺の石庭は、日本を代表する近代作家・志賀直哉のエッセイ「龍安寺の庭」(1924年)で取り上げられ、広く人口に膾炙したものである。かつ、このエッセイが第二次世界大戦後の中学・高校の教科書に取り上げられたので、日本人で知らない者は居ないだろう。日本庭園と言えば、まずこの龍安寺の石庭が挙がるのではないかと思う。

(写真1:龍安寺石庭 [1])
次の日本三名園は、これも日本を代表する名園として日本人に昔から親しまれて来たものである。日本三景(松島、天(あまの)橋立(はしだて)、厳島)、日本三名城(姫路城、松本城、熊本城)など、日本三何々で括られるものが、日本人に特に好まれることもあって、日本の名園と言えば、この三名園を挙げる人も多いはずである。三つ目は、京都とその周辺にある借景庭園である。後述するように、この「借景」は日本人好みの庭園様式であり、かつ日本の文化・文学・芸術を考える上でも極めて重要である。さらに、先に挙げた修学院離宮や円通寺などは、日本文化のセンターである京都やその付近にあって観光客も多い。多くの日本人にとって身近な庭園でもある。
今、日本庭園を代表する三つ(三つの範疇)を挙げてみたが、これらはそのまま日本庭園を代表する三つのスタイルでもある。
その三つとは、「枯山水庭園」(龍安寺の石庭)、「回遊式庭園」(日本三名園)、「借景式庭園」(修学院離宮や円通寺)である。次に日本庭園の歴史を辿りながら、そうした日本庭園の特質に迫るとともに、文化的背景、文芸との関係にも触れてみたい。
日本庭園の歴史
〈古代の庭園〉7世紀以前
いつ頃から日本に庭園が造られるようになったのかは、はっきりしない。古くからそうしたものがあった可能性もあるが、本格的に造られるようになったのは、藤原京や平城京など、中国大陸を意識した都市計画が行われるようになってからであることは間違いない。中国から朝鮮半島経由で様々な庭園作法(石組みや流水技術)が到来し、多くの庭園が作られたと考えられる。その中でも特徴的なのは、日本の庭園が海や水を強く意識していることである。
その代表に州浜(すはま)と須弥山(しゅみせん)石(せき)(噴水)がある。
州浜とは、庭園の池の畔に小石等を敷き詰めて、海岸をイメージする風景を作りだすものである。池の水の満ち引きによって様々に趣が変わることに特色がある。また、須弥山石は湧水を利用して噴水するもので、有名なものに藤原京の須弥山石がある。共に土地の高低差が激しく、そのことによって、水が豊富に得られる日本の環境を生かした庭園造りで、この特徴が後述するように、日本庭園の性格を大きく規定することになった。
〈平安時代の庭園〉8世紀~10世紀
794年に始まった平安京において、荘園によって富を得た貴族たちが、豪壮な家造り、庭造りを行った。これを寝殿造(しんでんづく)りと言う。この寝殿造りにおいて、どのような庭園が作られ、配置されていたのか、様々な議論があるが、重要な点は、後世『徒然草(つれづれぐさ)』を書いた吉田兼好も「家づくりは夏をむねとすべし」(家を建てる時は夏に合わせるべきである)と言ったように、日本(特に京都)の夏は蒸し暑く、貴族たちは如何にしたら清涼感を出せるか工夫した。そのために、池や滝、そこへ流れ込む流水や遣り水の配置が、ことのほか重要な意味をもった。また、寝殿造りの池は、舟遊式庭園とも言われ、船で遊べるほど大きなものであり、貴族たちはその舟の上で管弦などを催し涼をとった。また寝殿から続く回廊は池の水の上に張り出し、そこで簡単な釣りができる仕掛けなどを施した。
この寝殿造りの庭園を考える上で、象徴的な意味を持つ建物がある。泉(いずみ)殿(どの)である。泉殿とは泉が湧き出ている傍や上に建てられたもので、泉の清涼感を直接感じ取るための建物である。従来、この泉殿の位置については下図のように、釣(つり)殿(どの)(釣りをする館)と反対の位置に池に張り出すように考えられていた。しかし、泉殿は泉が湧き出す一種の井戸である。井戸を池の中に掘ることは考えられない。そうした批判があって泉殿の位置は長く分からなくなっていたが、庭園史家の太田静六 氏[2]が、邸宅の敷地内のどこに泉が湧き出すかは土地によって違っており、よって泉殿の位置もまた決めることができないと指摘し、論争に終止符を打った。太田氏によれば、京都は周囲を山に囲まれ、そこに降った雨水が地下に浸透し、それが京都盆地のここかしこで泉となって湧き出した、ということである。
ここで重要なのは、泉殿の位置もさることながら、日本の庭園が自然に湧き出す泉を中心にし、その景観が作られていたことである。事前に一定の形式や思想があり、それに合わせて庭園が作られるのではなく、まず自然の配置があり、それを生かす形で庭園が作られていたと考えられることである。この自然を生かす庭園造りの方法は、日本の文化・文学などを考える際にも極めて重要である。
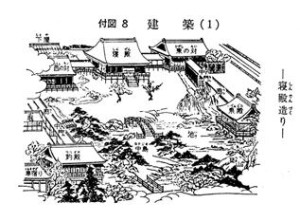
(寝殿造りと泉殿[3] )
〈平安時代末期から鎌倉時代にかけての庭園〉10世紀~12世紀
この時期を代表するのは、いわゆる浄土式庭園と呼ばれるものである。平安時代の貴族たちが深く信仰した宗教は仏教だが、その仏教の諸説の中でも、仏の教えが守られずに社会が崩壊するという末法思想が貴族たちの心を捉えた。それは丁度西暦1000年あたりから、末法に入ると言われたことや、実際に、長く続いた貴族社会が様々な形で混乱を見せ始めていたからでもあった。
こうした状況を踏まえて貴族たちは、現実世界(穢土)ではなく、死後の世界(浄土)に救いを求めるようになり、その浄土をイメージ化した庭園を盛んに造るようになった。代表的なものとしては、宇治平等院、平泉の毛(もう)越寺(つうじ)、いわきの白水(しらみず)阿弥陀堂(あみだどう)などである。宇治平等院は近くの宇治川から水を引き入れ、大きな池を拵えると共に、その中の島に堂(現在は鳳凰堂)を建て、極楽浄土としての蓬莱島を彷彿とさせるスタイルを取っている。この海に浮かぶ蓬莱島を連想させる方式は、毛越寺や白水阿弥陀堂などでも同じで、この世のものとは思えない幻想性を帯びた庭の姿が印象的である。
なお、橘(たちばな)俊(とし)綱(つな)(1028~94)作と伝えられる『作庭記(さくていき)』が書かれたのもこの時期である。この『作庭記』は日本最古の造園書であり、平安時代の寝殿造り様式を中心にしながらも、鎌倉時代以後に主流になる枯(かれ)山水(さんすい)様式にも触れているところが特徴で、平安時代から鎌倉時代への過渡期の様相を良く示している。『作庭記』全編を通して強調されるのは、「嶋」「池」「大海」「大河」「沼様」「滝」「遣水」「泉」など徹底的に「水」に繋がる世界である。と同時に、その刻々変化する「水」の世界に対置する形で、永遠を志向する「石」の世界が重視されている。
〈鎌倉時代から室町時代にかけての庭園〉13世紀~16世紀
鎌倉時代から江戸時代まで、日本を支配したのは武士である。平安朝は貴族社会であったために豪壮で煌(きら)びやかな世界が好まれたが、武士は清楚(せいそ)でシンプルなものを求めた。その武士たちの心を掴んだのが、仏教の禅宗を背景に持つ、枯山水様式の庭であった。
枯山水様式とは山水河原者と呼ばれる職人たちが作り上げる庭園で、極めて象徴的・抽象的な性格を持っている。枯山水とは、「山水」を「枯」らすことだが、それは「山水」の否定ではない。それはむしろ逆で「山水」の特に「水」を絶つことで、逆により強烈に「山水」を意識させるのである。
この枯山水様式の庭園が、遊興や休息の場ではなく、禅宗の座禅の道場、という思索上の達観・悟りの場で活用されてきたことが何よりも重要である。座禅をする者は、石や白砂の世界から、大海や大河、渓谷やせせらぎまでを自由に想像し、それらと一体化したところで空や無の境地に達するのである。そうした思索思惟、瞑想をするための庭園であるから、平安時代までの庭園のような広大な場所が必要なわけではない。この枯山水様式を代表する龍安寺の石庭を見た者が、異口同音にその狭さに驚嘆するのは、そうした背景があるのである。狭い庭園から広大な自然を感得する思索力がそこでは試されるのである。
言うまでもなく、庭園は自然を志向するものではあるが、自然そのものではない。そこには何がしかの象徴性・抽象性が施されるのであるが、日本の枯山水様式の庭園は、そうした意味で言えば、究極の庭園と言うことが出来るだろう。
またこの時期には、書院造(しょいんづく)りという建築様式によって、枯山水とは別の様式を持った庭園が発展した。書院とは元来、禅僧が本を読む為の場所であり、かつ居間であったが、これが武士の間にも広がり流行した。流行の背景には、武士は貴族とは違い、対面儀礼にこだわる性格を持っていた。御恩と奉公と言われるように、武士の上下関係は、貴族の上下関係が血筋であったのと違って、基本的には契約関係であった。その契約を確認するために対面儀式が重んじられたのである。よって書院造りの書院には、身分の上下を示す、上座下座の位置や、その位置を象徴的に示す床の間、また武士的な威厳を示すための書画や置物などを置く違い棚などが発達した。
更に、そうした書院の周囲では、対面儀礼を演出するための庭園が重視された。平安朝のような華美な庭園ではなく、あくまでも武士的な質素で清楚なものが求められた、と同時に、回遊式のものではなく、書院からの眺めがあくまでも重視されたのである。代表的なものとしては慈照寺の観音殿(通称は銀閣)とその周囲の庭園が挙げられる。
〈江戸時代の庭園〉17世紀~19世紀
永い戦乱が終息した江戸時代では、それまでの日本庭園が様々に試みた様式を総合する形での庭園造りが行われた。それが江戸時代の回遊式(かいゆうしき)庭園である。庭園は基本的には回遊するものであるから(前に述べた枯山水などは鑑賞するもので別個であるが)、回遊式というのは特別な呼称ではないが、ここで言う回遊式の特徴としては、池以外に中心となるものが無く、それぞれの部分・場所でそれぞれの趣を設(しつら)えていることである(よって「池泉回遊式庭園」などと言われる)。
たとえば中国を代表する庭園に、蘇州(そしゅう)の拙(せつ)政(せい)園(えん)と留(りゅう)園(えん)がある。共に中国の四大古典庭園と言われるものであるが、これらの庭園には中心がある。拙政園の中園、留園の五峰仙館や太湖石である。これらを中心に様々な庭園が東西南北に配置されている。よってこうした庭園の案内書などには、まず中心の場所に行き、その場を堪能してから他所へ回るべし等と書かれている。ところが、日本の江戸時代に作られた回遊式庭園には中心がない。池が中心を成してはいるが、それは何処からでも見えるので、センターとしての中心と言うよりは、むしろゼロ記号としての中心を成していると言って良い。
よって庭園の鑑賞者は、池の周囲を廻りながら、その場その場で様々な景観や自然との意表を突く、一回限りの出会いをすることになるが、その出会いはすぐに終わり、次の新たな出会いへと繋がって行くことになる。よく外国から日本に来た観光客が、日本庭園を見学する場合、どの場所から見れば良いかと尋ねることがあるが、その問い自体が日本庭園の場合、意味を成さないと言える。
この日本庭園の脱テーマ性、脱中心性については、日本文化全般の問題とも繋がるので、後ほどまとめて述べたいが、こうした回遊式庭園は、江戸時代の大名によって大掛かりなものが作られた。その代表が先にあげた日本三名園である。これらはどれも江戸時代を代表する雄藩(加賀藩、岡山藩、水戸藩)の大名庭園であるが、さらにこの時期を代表する大掛かりな回遊式庭園として名高いのが、江戸時代の六代将軍、家宣(いえのぶ)から代々に渡って将軍家が直接管理した浜(はま)離宮(りきゅう)(江戸時代には「浜御殿」と呼ばれ、明治時代以後、皇室の離宮となったことから、この名がある)である。この離宮は河ではなく、直接海からの海水を庭園に引き入れ、潮の満ち引きによって池の姿が変わるものであった。
浜離宮は、古代の庭園に志向された、象徴としての州浜が、リアルな州浜として完成した瞬間であったと言ってよい。
〈日本庭園の脱中心性と連歌・俳諧〉
古代から近世(近代)までの日本庭園の歴史を簡単に辿ってみたが、こうした日本庭園の持つ日本らしさが、日本の文学や芸術の世界と深い関係の中にあることを、以下の二つの問題を例にしながらまとめておきたい。
一つは、日本庭園の脱テーマ性・脱中心性と、連歌(れんが)・俳諧(はいかい)である。
いましがた述べた、日本庭園、特に回遊式庭園の脱テーマ性や、脱中心性は、日本文化全般の特色でもある。絵画・音楽・文学、どれにおいてもそうした要素が濃い。たとえば絵画であるが、日本画、特に水墨画(山水画)には、何も書かれていない余白(日本語に言う「間」)が多い。これは、書かれた部分、すなわち絵の中心世界を、脱化・朧化させる役割を負っていると言われる。また一見派手に見える浮世絵においても、絵を統括する視点は弱く、描かれた人やモノがバラバラに存在していることが指摘される。
文学では、この脱中心性はさらに強く志向されている。まず、日本の物語や古典小説には中心となる人物があまり居ない。居ても影の薄い存在である。たとえば、日本の物語を代表する紫式部作『源氏物語』には光源(ひかるげん)氏(じ)という男主人公が登場するが、彼は個性際立つ人物というよりは、周囲の女性たちの個性や美しさを映し出す、当に「光」のような存在である。また古典小説を代表する井原西鶴作『好色一代男』の主人公世之(よの)介(すけ)も同じであり、作品後半の遊女列伝において世之介は、遊女の引き立て役に徹するのである。
こうした脱中心志向を、内容のみならず、形式としても志向したのが、連歌と俳諧(俳諧の連歌)であろう。連歌は一人で詩を作るのではなく何人かで合作する詩の形式である。全体を統一するテーマ(主題)を置かずに、第一の詩(発句)→第二の詩(脇句)→第三の詩(第三)と順番に展開し、連想ゲームのようにして「詩」が繋がってゆくのである(基本的には百句[百(ひゃく)韻(いん)と呼ばれる])。
連歌には全体を構成するテーマや中心が無く、参加者(連衆と言う)の連想によって如何ようにも展開するのであって、最終的にどのような作品になるかは終わるまで全く分からないのである。この脱中心性と、その場その場での出会いと変化という一回性は、回遊式庭園の鑑賞の仕方と全く同じである。
この連歌は、日本の平安時代から室町時代にかけて貴族や上流の武士たちを中心に流行したが、室町時代以降、庶民の間にも広がると、従来の連歌にはなかった庶民的で卑俗な内容を盛り込んだ俳諧(俳諧の連歌、基本的な長さは三十六句[歌仙(かせん)と言う])に転化し、全国的に広がった。この連歌と俳諧が広がりを見せた時期と、日本において回遊式庭園が盛んに造られた時期は丁度重なっている。
〈日本文学の借景性〉
もう一つは、日本文学の借景性である。
「借景」という語は、元々造園用語で、中国明代の『園冶』(計成、1634年)に「夫借景、林園之最要物也」とあることから重要視されてきたが、周宏俊によれば、中国の明代以前では、他人の庭を俯瞰する、生け捕る「借景」としての「借景亭型(しゃっけいていがた)」と、部屋の窓などから外界を視る「尺幅(しゃくふく)窓型(そうかた)」の「借景」が主流であって、「小中(しょうちゅう)見(けん)大(だい)」即ち「小」の中から「大」を望む「遠望型」を意味する「惜景」の語は近代に入ってから主に用いられるようになったらしい。造園用語としてはまだ不確定な要素があるとのことでもある。

(写真2:修学院離宮[4] 庭園から遠方の山を望む)
しかし、日本の庭園にこの遠望型の借景庭園が多く存在することは確かであり(先に例として挙げた修学院離宮や円通寺)、「小中見大」借景の、ものの見方、捉え方が日本文化の基軸にあることも確かであろう。周宏俊氏 [5] は日本文学・文化の借景性についての代表的見解として、大輪靖宏氏[6] と柄谷行人氏[7] の名を上げる。
大輪によると、俳句は独立した価値を持っている文学形態であるとともに、与えられた背景の違いによって味わいが変化することが文学的な長所という。つまり、俳句は日本の借景庭園と同じように背景と敏感に反応し合うという特徴である。(中略)柄谷行人によると、庭園の借景は外的な風景が庭を通して見られることであり、巨大な自然を一種のレンズを通して縮小することに当たり、さらにいえば、庭園は表象装置である点で絵画や文学と共通しているとされる。
俳句は世界最短最小の詩である。その短さや小ささの持つ限界を補うのが、俳句の前後に置かれた詞書きや、俳句が作られた場所や背景などであり、その俳句と詞書き・背景の響き合いの中にこそ俳句文芸の骨頂がある。そしてその俳句と背景の関係は、まさに庭園と借景の関係に他ならないと大輪氏は言う。柄谷氏は大輪氏とは逆に、庭園の小ささはレンズであり、そのレンズを通して外界としての借景は整理・馴致され、意味を与えられると言う。大輪氏が庭園と借景の関係性に注目し、柄谷氏は庭園の縮小性に注目したという違いはあるが、両者ともに日本借景庭園の「小中見大」に注目し、それが日本文学の基底にあると指摘することは共通する。
この日本の借景庭園の特色は、韓国の庭園と比較すれば、よりはっきりとするであろう。従来から、韓国には中国や日本のような際立った庭園形式が見当たらないと言われてきた。しかしそれは誤りである。たとえば昌徳宮の秘苑を見れば良い。ここには、確かに中国の江南蘇州や日本の京都にあるような借景庭園や回遊式庭園はない。そのような仕掛けは一切ないのである。むしろ、そのような仕掛けを作らないことが韓国庭園の特徴だと言ってもよい。
朝鮮時代に支配的だった儒教(朱子学)は、世界は理気と陰陽五行で出来ており、その条理を十全に発揮させることが重要だと説いた。儒教にとって、目の前にある世界そのものが理想を追究する場であって、仏教で言うような浄土や蓬莱島を別個に造り上げる必要はなかった。すなわち、儒教的観点からすれば、昌徳宮の裏山全てが庭園であった。よって、必要なのは自然そのままを観察できる東屋であった(秘苑には特筆すべき東屋がいくつもある)。
この問題を李御寧氏 [8] は、八角亭という八方に開かれた東屋を例にし、かつ日本庭園と比較しながら次のように述べている。
日本人は、自然を自分の庭の中に引っ張ってきて庭園芸術を作ったが、韓国人は直接外に出て自然そのものを芸術として作りあげる八角亭の風景の美学を作り出した。八角亭に座ってみると、自然そのものが屏風になり、庭園になる。東屋から周囲の景色を取り去ることができないように、人間と自然が深い関係において分離することができない、一つの絵を作り出しているのだ。
この日本と韓国の違いが、日韓文芸の違いにそのまま表れていることは言うまでもない。日本の俳句と比較されることの多い、韓国の時調には、自然と一体化した人間(作者)の姿が強く映し出される。それに対して、日本の俳句は、李御寧氏が言うように、対象から一部を切り取り(写生)、そこに象徴的な意味を持たせる。俳句が目指すのは、対象との一体化ではなく、一定の距離を置いた異化、他者化と言って良い。日本の俳句と韓国の時調、同じ自然を対象にしていても、自然に向かい合う姿勢はまるで違うのである 。(了)
注
[1] 岡田憲久『日本の庭ことはじめ』TOTO出版、2008年
[2] 『寝殿造の研究』吉川弘文館、1987年
[3] 『明解古語辞典』(昭和46年版)所載の寝殿造りの図
[4] 注1と同じ
[5] 「借景の展開と構成―日本・中国造園における比較研究」2012年3月、東京大学博士論文(森林科学専攻)
[6] 「俳句の借景性」『芭蕉俳句の試み』南窓社、1985年
[7] 「借景に関する考察」『批評空間(Ⅱ期)』17号、1998年4月
[8] 「八角亭」『韓国的思考』スカイ出版、2010年
(参考文献)
William Chambers『東方造園論』邱博舜訳注、原書1773年、訳注2012年
上田篤『日本人とすまい』岩波新書、1974年
楊鴻勛『江南園林論-中国古典造園芸術研究』、上海人民出版社、1994年
宮元健次『図説日本庭園のみかた』学芸出版社、1998年
林屋辰三郎『作庭記』リキエスタの会、2001年
進士五十八『日本の庭園―造園の技術とこころ』中公新書、2005年
西桂『日本の庭園文化』学芸出版社、2005年
上田篤『日本人の心と建築の歴史』鹿島出版会、2006年
上田篤『庭と日本人』新潮新書、2008年
小野健吉『日本庭園―空間の美の歴史』岩波新書、2009年
阿部茂『日本名園紀行』竹林館、2009年